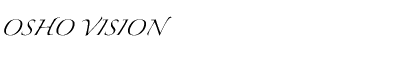OSHO 講話
“究極の問い“
真の仏性、いっさいの功徳の根は覚性であると言われますが、無明の根とはなんでしょう?
ボーディダルマは、かつて誰ひとり答えることができなかった究極の問いに直面している。究極の問いが究極であるのは、それに答えることができないからだ。あらゆる哲学、神学、神秘主義は最終的にはこの究極の疑問にぶつかる。そして、それに対する答えはない。
だが、ボーディダルマのような底なしの勇気と、知性と、〈気づき〉を持った人ですら、この問いには答えがないと言うだけの勇気を持ち合わせては いない。彼はなんとか答えようとする――ちょうど何百万もの哲学者、思想家、神秘家たちが絶えずそれを試み、そしてつねに失敗してきたように。
彼もまた、あたかもその答えがあり、自分はそれを知っているのだと言わんばかりに試みる。だが、彼の言っていることは何ひとつ答えにはなってい ないし、問いそのものには少しも手がつけられないままだ。彼の言っていることは、まさに仏教の諸経典に書かれていることであり、彼はもはや、問いに対して 自らの〈気づき〉からは応じていない。もし応じていたなら、彼はただ笑って、この質問には答えがないのだという事実を認めていただろう。
私なら、たんに「知らない」と言っていたはずだ。だが、「私は知らない」と言うためには、この世における最大の勇気が必要とされる。ボーディダ ルマですら、その究極の勇気を持ち合わせていなかった。だが、私にはある! 私は、どのような形でもごまかしの手を使い、哲学的な専門用語や神学的仮説に よって答えがないという事実を覆い隠し、回答の幻影を生み出そうとはしない。
ボーディダルマがここで言っていることは、すべて虚妄だ。彼はそれを合理化しようとしている。経典に支持を求めようとして、あらんかぎりの手を尽くしている。彼はたぶん弟子たちをなだめることはできただろうが、私をなだめることはできない!
まず最初に弟子の問いを読もう。彼らの問いは、ボーディダルマの答えよりもはるかに重要だ。少なくとも彼らの問いには正直さ、真正さがある。ボーディダル マの答えは、究極の問いは疑問のままにとどまるのだという事実を、ただ覆い隠そうとするものでしかない。本質的な宗教が「神秘主義」と呼ばれる理由は、ま さにそこにある。あらゆるものに答えがあるのだとしたら、神秘というものはひとつもなくなってしまう。
〈存在〉は神秘的だ。さまざまな疑問に次々と答えていったとき、その最後に至って、あなたはこの答えることのできない究極の問いに直面する。し かもそれはずっと先のことではない。それはすぐに浮かび上がってくる。あなたはあらゆる表面的なものごとについて答えることができるが、少し先へ進めば、 この究極の問いが近づいてくる。だが、究極の問いがやって来たとき、「私は知らない」と言うだけの勇気を持ち合わせていた者は、私の知るかぎり、人類の歴 史全体を通じてただのひとりもいなかった。
その質問だ――
「真の仏性、いっさいの功徳の根は覚性であると言われますが、無明の根とはなんでしょう?」
この〈無明〉はいったいどこから入り込んだのか? ほかの言葉、ほかの象徴を使った問いならもっと理解しやすいかもしれない……。
神の存在を信じる宗教が、さまざまな問いに答えていったとき、「では、誰が〈存在〉をつくったのか?」と尋ねられる地点がやって来る。彼らはそ のための既成の答えを用意している。「神がつくったのだ」と。だが、そこで究極の疑問が生じてくる「では、いったい誰が神をつくったのか?」なぜなら、あ らゆるものに創造主が要るなら、神にも創造主が要るはずだからだ。だが、もし神には創造主など要らないと言うなら、どうして神のことなど気にするのか? だったら、なぜ〈存在〉をそのままの形で受け容れないのか――創造主などなしで。いずれにしてもどこかで受け容れねばならないのなら、〈存在〉を究極のも のと見なして、そこで止まったほうがよい。なぜなら、私たちは少なくとも〈存在〉のことなら知っているからだ――私たちはその一部だ。
神はたんなる仮説にすぎない。〈存在〉は実在する。だが、あらゆる宗教は実在するものから仮説へと乗り換えてしまったせいで、かつてひとりも答 えることのできなかった難問に直面するようになった。これからもそれに答えることができる者は現われないだろう。というのも、どんな答えを与えようと、そ れは新たな疑問を生み出してしまうからだ。
たとえ第一の神は第二の神によってつくられたと言っても、疑問は依然として解消しない。「では、誰がその第二の神をつくったのか?」これをえん えんと続けていくこともできる。だが、番号がいくつになったとしても、あいかわらず「誰がその神をつくったのか?」という問いは生きている。それは最初の 出発点である、「誰が宇宙をつくったのか?」という疑問と同じだ。
だから、「神」はいかなる助けにもならない。その仮説は少しも役には立たなかった。「神」はまったく無用な仮説だ。いかにも答えのように見えるが、疑問が残るのだから真の答えではない。真の答えは、疑問を解消させるものでなければならない。それが判断の基準だ。
仏教には神というものはない。神があるべき位置には、究極の〈気づき〉、ブッダの境地、仏性がある。これらは言葉は異なるが、みな同じものを指している。
さて、弟子たちは尋ねている―― 真の仏性、いっさいの功徳の根は覚性であるということは理解できます。しかし、どこから無明が 入り込んだのでしょう? なぜ最初に無明があったのでしょう? なぜそもそもの始めから〈気づき〉がなかったのですか? これは同じ問いであり、神学的な 枠組みが異なっているだけだ。そして、これに対してはいかなる答えも――まったく聞いたことのない答えであろうと、ひとつの例外もなく――すべてが間違い になると私は言うことができる。
人は無明のなかに生まれるが、人にはその無明を払いのけて、〈気づき〉を持つようになる可能性も最初からそなわっている! 私たちはこの神秘をただ受け 容れるしかない。私たちは惨めさのなかに生まれるが、同時にそれに打ち克ち、それを超越し、至福に満ちるようになり、歓喜にあふれるようになる潜在的な能 力もそなえている。私たちは死のさなかに生まれるが、同時にその死を乗り越えて不死に至る可能性も秘めている。
だが、死はどこから入り込むのか、無明はどこからやって来るのか、惨めさはどこから生じるのかと尋ねるなら、あなたは究極の問いを尋ねている。 それに対する答えはない。それはただそのようにある。仏陀の表現を使うなら、それが〈あるがまま〉(真如)だ。ものごとはただそのようにある。
だが、ボーディダルマはそれを言うことができなかった。彼はそれに答えはじめた。唯一の正しい答えは、「私は知らない」だったはずだ。もしそう 答えていたら、ボーディダルマは人類にすばらしい貢献をしていただろう。彼はその機会を逃してしまった! 彼の言っていることはまったくもって幼稚だ。そ れもそのはずだ。ボーディダルマほどの人が、自分が答えを知らないという事実に気づいていないことなどありえないからだ。誰ひとりその答えを知る者はいな い。〈存在〉の始まる前に存在した者など誰もいないのだから、その答えを知ることは誰にもできない。
ちょっと考えてみなさい。人は原初よ りも以前に存在することはできない。誰かが〈始め〉よりも以前に存在したなら、それはもはや〈始め〉ではない。誰かがすでにそこにいるなら、真の〈始め〉 はその人が存在するよりも前ということになる。だが、誰かが〈始め〉よりも前に存在しないかぎり、誰も「神がこの世界を創造した」と証言することはできな い。
無明がどこからやって来たのかを教えられる者がいるだろうか? 私たちにせいぜい言えることは、〈存在〉は無明のなかに溺れているが、何人かの勇気ある人びとが少しずつ〈気づき〉の方への動いてゆき、生の暗黒を超越して永遠なる光を達成する、ということだけだ。
別の経典のなかで、ゴータマ・ブッダはそれをはっきりと言っている。彼もやはり、それが神秘であること、自分は知らないという事実を、いかなる点でも認めてはいないが……。
私はあなた方に、それが神秘にとどまること、これからもつねに神秘にとどまるであろうことを理解してほしい。まさにその本性からして、〈始め〉を知る方法はない。
だが、別の文脈において、仏陀はそのきわめて近くに至る。彼は言う。「無明には始まりがないが、終わりがある。そして意識には始まりがあるが、 終わりがない」彼はそのような言い方で、この円環を完結させる。もっと深く感じ取れるよう、もう一度くり返そう。無明には始まりがないが、終わりがある。 そして、無明に終わりがあるために〈気づき〉には始まりがあるが、それには終わりがない。〈気づき〉はいつまでも永遠に続いてゆく。
仏陀はこの言明をもって、無明の始まりについては尋ねないほうがよいし、〈気づき〉の終わりについても尋ねないほうがよいことを明らかにしている。この二つは永遠に神秘にとどまる。そしてこれらのことは、〈存在〉にまつわるもっとも重要なことがらだ。
もしこの問いが私に尋ねられたなら、私はただこう言うだろう。「私は知らない」と。それがもっとも誠実な答えだ。それが意味するのは、それは神秘であるということだ。
だが、ボーディダルマは、この問いに答えようとしはじめる。それが問いに触れるものですらないことは、誰の目にも明らかだ。
無明の心……
問いは、「無明はどこからやって来たのか」ということだった。彼はそれに答えるどころか、最初から無明の存在を受け容れてしまっている。無明の心、その限りない煩悩や情欲や悪徳は、怒り、妄想に根ざしている。
これが答えと言えるだろうか? 彼は、無明の心はそういった一定のものごとに根ざしているのだと言っている。妄想と、怒りと、貧欲に。だが、これが答えだろうか? 弟子はそんなことを尋ねただろうか? 彼はほんとうにこんなたぐいの説明を求めたのだろうか?
質問は「無明の根とは何か?」ということだった。「無明の根は貧欲、怒り、妄想だ」と答えても、あなたはたんに答えることを延ばしたにすぎな い。再び疑問が起こってくる。「では、貧欲はどこから生じるのか? 怒りはどこから生まれ、妄想はどこからやって来るのか?」そうなると、あなたは悪循環 にはまり込んでしまう。今度は、あなたはこう答えはじめる。「それは無明から生じる。人間の無明が原因だ。人間に貧欲があり、怒りがあり、妄想があるのは そのためだ」そこでまた「では、無明そのものはどこからやって来るのか?」と尋ねると、答えは「無明は怒りから、貧欲と妄想から生まれてくる」ということ になる。いったいそれで、誰をだまそうというのか?
だが、何世紀にもわたって、人びとはこういったたぐいの答えにだまされつづけてきた。おそらく誰ひとりとして、このような的外れな答えに疑問を 投げかけた者はいなかった。たぶん彼らは、ボーディダルマのような人物の個性にあまりにも深い感銘を受け、完全に圧倒されてしまったのだろう。あるいは、 おそらく人びとは、ボーディダルマがこの問いの周囲に煙幕を張ってしまい、問いそのものをぼかしてしまったことを見抜けなかったのかもしれない。おそら く、そのどちらかだろう。彼は人びとの目のなかに塵を投げ込んでいる。それは答えではない。
だが、これはボーディダルマの場合だけにとどまらない。誰についても言えることだ……ゴータマ・ブッダ、マハーヴィーラ、孔子、老子、ツァラツ ストラ、イエス、モーゼ……ひとりの例外もなく、あらゆる人びとに。究極の問いに近づくやいなや、彼らは意味もないことをしゃべりはじめる。彼らこそもっ とも賢明な、もっとも知性的な人たちであるはずなのに。
知性は究極の問いに答えることができない。ただ無垢だけが、それに答えることがで きる。無垢な人、他人の評判も、知恵も、〈光明〉(エンライトンメント)も、なにひとつ気にかけない人、自分の誠実さのためにあらゆるものを犠牲にできる 人にして初めて、それに答えることができる。
これらの人びとは、自分の知恵を危険にさらすことができなかった。彼らは「私は知らない」と言うことができなかった。だが、それこそ唯一の真正 な答えだ。なぜなら、あなたはそれを聞いたとき、自分は究極のものに至ったと感じることができるからだ……。ここからは神秘が始まる。それを解き明すこと はできない。それを知識におとしめてしまうことはできない。それは努力や知性や修業や訓練や、なんらかの技法や儀式によって知ることができるものではな い。
その神秘を生きることはできるが、それを知ることはできない。それはつねに〈知られえぬもの〉にとどまる。それはつねに神秘にとどまる。
私たちの偉大な同時代人のひとりにG・E・ムーアがいる。彼はブリンキピア・エチカ『道徳原理』という本を書いた。おそらく歴史全体を通じて、彼ほど深く 「善」という言葉の定義を考えた人はいないだろう。というのも、善とはなんであるかを定義しなかったら、いかなる倫理も道徳も成立しえないからだ。善とは なんであるかを定義できなかったら、どうやって道徳とはなんであり不道徳とはなんであるかを定義できるだろう? どうやってなにが正しくなにが誤っている かを定義できるだろう?
彼はそれが究極の問いであることを知らずに、この根本的な疑問を取り上げ、そして窮地に陥った。彼は、現代の世界におけるもっとも知性的な人び とのひとりだった。彼はそれについてあらゆる角度から考察し、延々250ぺージにもわたって 考究した。このただひとつの疑問、「善とはなにか?」を解く ために。そして、これほど単純な言葉である「善」を定義することにおいて、彼は完全な敗北を喫した。誰でも、善がなんであるのかを知っているし、なにが悪 であるのかを知っている。誰でも、なにが美しいのかを知っているし、なにが醜いのかを知っている。だがその定義となると、誰もがかならず同じ窮地に陥って しまう。
クローチェは、これと同じ仕事を「美」について行なった……しかも千ぺージにもおよんで。彼はG・E・ムーアが「善」において至った地点よりも、はるかに深いところにまで達した。だが、千ぺージも費やしたあとに、この最後の言明がある「美は定義することができない」
なにが美しくなにが醜いのかを知らない人間を見つけるのはきわめて難しい。それがほとんど不可能であることは誰でも知っている。しかし、定義に固執すべきではない。もっとも偉大な頭脳ですら失敗している。
私自身が理解しているように、すべてのものは定義できないのだ。なぜなら、あらゆるものが神秘的だからだ。それはたんに美や善、無明や〈気づき〉といっ た問題に限ったことではない。あらゆるものがそうだ。〈存在〉はすべて定義されざるものから成り立っている。それを認識することは、私たちの究極の無知を 認識することだ。そして、自分の究極の無知を認識するためには、絶対的に私心のない意識、エゴのない無垢な意識が必要になる。なぜなら、それが失われてし まっているからだ。
ボーディダルマは、ほかのあらゆる者たちがやったのと同じことをやっている。それは少しも新しいことではない――何世紀にもわたって、哲学者たちはそういった些細な問題に溺れ込んできた。
私たちの時代、そしてたぶんすべての時代を通じてもっとも偉大な数学者のひとりであるバートランド・ラッセルは、『数学原理』(フリンキヒア・ マセマティカ)という本を書いた。「2たす2はほんとうに4なのか?」という疑問を吟味するのに、彼は250ぺージを費やしている。その250ぺージの中 になにが書かれているのか、あなた方にはほとんど想像もできないだろう……。ふつうの人なら「とにかく2たす2は4だ。あとはきれいさっぱり忘れてしま え」ということになる。だから、このことを覚えておくべきだ。私はこれらのボーディダルマの回答にざっと目を通すが、それらは答えではない。それらに目を 通すことは、なにかの役に立つかもしれない――あなた方がほかのなにかを理解するための助けになるかもしれない。だが、それらは問いの答えではない。
しかし、それはボーディダルマの罪ではない。答えは存在しない。彼のただひとつの罪は、自分が知らないということを自ら認めなかったことだ。そ して私は、そのことについては彼を許すことができない。なぜなら、私は彼のことを愛しているし、彼を尊敬しているし、彼には誠実であってほしいからだ。も し彼が「私は知らない」と言っていたら、彼はほかの何千もの神秘家や覚者(ブッダ)、ボーディサットヴァやアルハトたちをはるか眼下に見下ろす高みにまで 昇りつめていただろう。彼は完全に独自な存在になっていただろう。だが、彼はそれを果たすことができなかった。
無明の心、その限り ない煩悩や情欲や悪徳は、三毒、すなわち貧欲、怒り、妄想に根ざしている。ひとつの幹に数多くの枝葉をつける大樹のように、心の十二毒の内にはいっさいの 諸悪が含まれる。だが、三毒それぞれから、さらに何百万もの悪徳が生ずるのだから、樹木のたとえはほとんど用をなさない。三毒は、人の六感覚中に六識、ま たは六賊として現われる。六賊と呼ばれるのは、六識が諸感覚の門を出入りする際、よろずのものを貧り、悪業を成すあまり、ついにはその真の本体を覆い隠し てしまうからだ。だが、誰かその本源を断つ者があるなら、この川は干上がってしまう。解脱を求める者が、三毒を三組の浄戒に、六賊を六波羅蜜(パーラミ ター)に転じうるなら、これをかぎりにいっさいの苦海を離れ去る。
これらはすべて、問題はない。
だが、はたしてこれは問いの答えだろうか? たしかにここに語られていることは真実だ。もし自らの貧欲、怒り、妄想――三つの毒――を〈気づ き〉によって変えることができたなら、それは甘露(ネクター)に変容される。あなたの病だったその同じものが、あなたの健康になる。あなたの束縛だった同 じものが、あなたの自由になる。必要とされるすべては、自らの存在の暗闇に〈気づき〉をもたらすことだ。
たしかにそれは真実だ。私たちはすでにそれについて、何度も何度もさまざまな角度から論じてきた。だが、それは「無明はどこからやって来たのか?」という問いの答えではない。
次のこともやはり真実だ。樹は根を断てば枯れてしまう。そしてあなたの束縛や盲目性や愚かさの根は、あなたの心(マインド)だ。もしあなたが心 の根を断てば……心の根とは、自分自身との一体化のことだ。腹が立っているとき、あなたは「私は怒っている」と言う。これがその根だ。腹を立てているとき も、ほんとうに気づいているなら、あなたは「私は怒っている」とは言わないだろう。「私は自分の心のなかを怒りが通り過ぎてゆくのを見ている」と言うだろ う。もしそれを言うことができれば、あなたは見ている人、目撃者だ。そのとき、根は断たれる。
目撃者でいることは、まさにその根を断つことであり、かくしてあなたは解放される。これは完壁に正しい。だが、これもやはり問いに対する答えではない。
私はボーディダルマが必要もない無駄話、”冗長な閑文”を語りつづけている事実を、これからも指摘してゆきたい。おそらく弟子たちは問いのこと などすっかり忘れてしまったのだろうが、私は忘れることができないし、彼を許すこともできない。彼の語っていることは、すべてほかの文脈においては正し い。彼はなにひとつ間違ったことを言っているわけではない。だが、彼がなにを言っているにせよ、それがいかに正しかろうと、それはまるっきり問いとは無関 係だ。正しければよいというものではない。答えは、問いとなんらかの関係を持っていなければならない。
私がここで言いたいのは、誰ひとり その問いに答えた者はいないということだ。なぜなら、生はひとつの神秘だからだ。あなたはきわめて遠くまで行けるが、ある地点で心のすべてを置き去りにし なければならない。そしてあなたは、あらゆる問いが意味を失う、なにひとつ答えがやって来ない〈存在〉のなかへと入り込んでゆく。
だがあなたは、その体験をこのうえもなく楽しむことができる。私は知識には反対だが、体験には大いに賛成だ。
私はボーディダルマのことで悲しみを覚えるし、彼のことを気の毒だとも思う。なぜなら、彼は私を失望させてしまったからだ。もし「私は知らない」と言っていたら、彼はこれまで世界が知りえた最高の、もっとも偉大な神秘家になっていただろう。
だが、私はここで言いたい。私は知らない。そして私は、誰もがそれを覚えておくべきだということを力説したい。いつであれ究極の問いに出会った ときには、自分や他人を欺こうとしてはいけない。たんに自分の無垢を受け容れなさい。謙虚さをもって言うことだ。「私は知らない」と。
これは無知であるか否かという問題ではない。これは生がひとつの神秘であり奇跡であることに気づくかどうかの問題だ。それを味わうことはできて も、その味わいについてはなにひとつ表現することはできない。誰にもそれを定義することはできない。まさにそれが〈存在〉のすばらしさだ。あらゆる科学者 たちが失敗してきたのはそこのところだ。あらゆる哲学者たちが失敗してきたのもそこのところだ。この地点において成功したのは、ただ神秘家たちだけだっ た。
ボーディダルマは神秘家だ。もし彼が私に会うようなことがあれば……この永遠の生、終わりなき〈存在〉のどこかには、きっとその可能性があるだ ろう。いつの日か、どこかの場所で、私は彼をつかまえるだろう。そして彼は、私が誰なのかわかるにちがいない。というのも私は、彼が自分の杖に結わえてい たのと同じ草履をはいているからだ――きっかり同じ種類のものを。私の草履は日本の禅院から来た。これは”禅”そのものだ――禅の人びとが所持している物 にはすべて独自性がある。彼らの使っている茶碗と皿は、たとえそれが市場から仕入れたものであっても、彼らはまずそれらを割ってから、また再びひとつにつ なぎ合わせて使う。そうやって彼らはそれを独自なものにする。そうしたら、ほかにそのような品物はひとつもない――それは”禅”になる。オリジナルなもの になる。それと同じものはどこを探しても見つからない。まさにそれひとつしかない。
あなた方の目にしているこの草履は、ボーディダルマ以来、ずっと禅の人びとに使われてきたものだ。ほとんど1400年の長きにわたって。この草履は最初、日本のある禅師から私に贈呈された。
だから、彼はただちに私のことを認識するだろう。私はただ彼に自分の草履を見せればよい。そしてそこで、私は聞かねばならない。なぜあれほどす ばらしい機会を逃してしまったのか、と……。彼は世界でいちばん優れた神秘家になることもできた。彼にはそれを満たすだけのあらゆる能力があった。彼には その天分があった。
邦題『ボーディダルマ』めるくまーる刊
copyrigh 2016 OSHO International Foundation