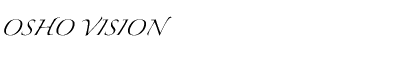OSHO 講話

サマサティ: 最後の講話
SAMMASATI :THE LAST DISCOURSE
The Zen Manifest:Freedom from oneselfより
愛する OSHO、
洞山は、無生物が法 を説いているかどうかについて疑問を持っていた。
洞山が為山を訪れると、為山は彼に雲巌の所に行くように勧めた。
雲巌の許で、洞山は初めて真理を知り、自分の経験を記録するために次のような偈を作った。
「素晴らしきかな! 素晴らしきかな!
無生物も法を説く――何という言語に絶した真理か!
耳で聞こうとすれば、けっして理解することはできない。
眼に聞こえて、初めて本当にわかる」
雲巌は彼に、「嬉しいか?」と訊いた。洞山は答えた。
「嬉しくないとは言いません。
しかしその嬉しさたるや、ゴミの山に輝く真珠を見つけたようなものです」
光明を得てしばらくして後、洞山は中国全土を旅しつづけた。
ある日、彼はレイ潭に着き、初首座に会った。初は、洞山に挨拶して言った。
「素晴らしや、素晴らしや――道と仏 の世界は測り知れぬ!」
洞山は「わしはそういう世界のことは知らぬ。そういうことを語っているそなたは誰か?」と応えた。
初首座が黙したままなので、洞山は、「言え!」と声を上げた。
それで初は「急かせてはいけません。それこそ道を逃すやり方」と言った。
「口にもされておらぬものを、急かせるも、見逃すもあろうか?」と洞山。
初はそれに応えられなかった。
そこで洞山は、「仏と道――次に君は経について語るだろう」と言った。
初は「これについて経には何とあるか?」と応えた。
洞山は「何もかもわかったら、言葉は忘れる」と言った。
初は「それは心の病」と言った。
洞山は「この病は軽いか重いか?」と言った。初は洞山に応えることができなかった。
友よ、
経文の前にサニヤシンから二、三質問が来ている。
最初の質問だ。
ドイツの有名な元女優ゲスタ・イタールは、日本の禅寺に入って、光明を得た導師の許で修行することを許された初めての西洋の女性でした。
彼女は自分の歩んだ道と悟りの経験について二冊の本を書きました。その本を読んだとき、私はそれが非常に厳しい孤独な道だという印象を受けました。あなたの許に
いることは、もっとずっと楽しい、遊びに満ちたことです。この違いについて何か話していただけますか?
伝統的な禅は厳しい。それには、すべてを擲 ち全エネルギーを瞑想にだけ捧げて、絶えざる瞑想を続けてもなお二、三○年はかかる。
その伝統はゴータマ・ブッダ本人から来ている。彼は自分の光明を見いだすために一二年の厳しい修行をしなければならなかった。
私がそれを伝統的な禅とはまったく別物に変えているのは、現代人が二、三○年を瞑想だけに捧げることができるとは、私には思えないからだ。そのように厳しいままだったら、禅はこの世から消えてしまうだろう。それは既に中国から消えてしまったし、日本からも消えようとしており、またインドではとうの昔に消えてしまった。インドには、ゴータマ・ブッダの後、わずか二五○年しかとどまらなかった。五世紀の後、それは中国に到達したが、そこには二、三世紀しかとどまらずに日本に移った。
そして現在、それは中国と日本の両方からほとんど絶滅しかけている。私の本が禅の僧院で教えられていると知ったら、みんなは驚くだろう。禅の導師たちが私に「おそらく今や禅はインドに、元の場所に存在することになるのでしょう。それは日本からは消えつつあります。なぜなら人々の興味はテクノロジーと科学の方に向けられているからです」と手紙に書いてきている。
それはインドにおける状況でもある。内面の探求に関心を持つ人々はきわめて僅かしかいない。あなたたちはここで、あらゆる国々からの僅かな人たちを見ることができるが、それはこの地上の五○億の人類に比べればごく僅かでしかない。一万人はたいした数ではない。
禅は現代人が興味を持てるようなものに変容されなければならない。それは簡単な、またくつろいだものでなければならない。厳しいものである必要はない。そういう古い伝統的な型はもはや可能でもないし、またその必要もない。一度その道が探検されたら、いったんひとりの人間が光明を得たら、その道は容易なものになる。電気を何度も何度も発見する必要はない。一度発見されたら、人はそれを使うことを始める――大科学者になる必要はない。
電気を発見した人間は、そのためにほとんど二○年を費やした。三百人の弟子が彼と一緒に仕事を始めたが、あまりにも長くかかったために最後まで残った者はひとりもいない。みんなくたびれ果ててしまった。だが当の科学者自身は仕事を続けた。彼が自分の弟子に言った説明はこうだった。「電気の根源が何であるかを見つけることに失敗すればするほど、私たちはその根源そのものに近づいている。失敗するたびに私たちは発見に近づいているんだ」と。
そしてついにある夜、闇の中に突然最初の電球が光を放ち始めた。三○年間研究してきた人間の喜びは想像することもできない。その沈黙‥‥彼は畏怖の念に打たれていた。あれだけの時間をかけた後、ついにそれが起こったこと、電気を制御できるようになったことが、わが眼で見ながらも信じられなかった――「ついに手に入った。これをどう使うか、だ」
妻が彼を呼んだ。「もうお休みになったら、もう真夜中よ。明かりを消して頂戴!」 彼女はそれが当たり前の明かりではないこと、そしてその科学者が彼女をこう呼んだことに気がつかなかった。「こっちへ来て、地上初めての物の最初の証人におなり。
お前が、電気の秘密に私が招待する最初の人間だよ」今では、電気のことを知るために三○年研究する必要はない。同じように、禅を経験するために三○年間を費やす必要はないのだ。
覚者たちの目覚めとはごく簡単なくつろいだ現象だ。今やあまりにもたくさんの人たちが目覚めたために、その道は明確なものになった。それはもはやきついものでも苦しいものでもない。あなたたちは遊びながらその内側に入り、その意識の目覚めを喜びを持って経験することができる。それはゴータマ・ブッダにとってそうであったようには、かけ離れたものではなくなった。
ゴータマ・ブッダにとっては、それはまったく未知のものだった。彼は盲人のように、自分がどこに向かっているのかをまったく知らずにそれを求めていた。だが彼は途方もない勇気の人だった。彼は一二年間、当時自分の手に届いたあらゆる方法を試みた‥‥哲学やヨガについて語る教師たちをすべて訪ね、探求した。彼は次々と教師を訪ね続けた。そしてあらゆる教師はついに彼に、「私はあなたにこれしか教えることはできない。これ以上のことは私も知らない」と告げたものだった。
ついに、彼は独りになり、ヨガの修行をすべて捨てた。彼には、彼のことを偉大な苦行者だと思っている五人の弟子がいた。だがその弟子たちは、彼がヨガの修行をすべて止め断食もしなくなったのを見て、彼を見捨てた。その五人の弟子たちは全員、「あの人は堕落した。もう聖者ではない。あたりまえの人間になってしまった」と言って彼の許を離れた。
だが何もかも捨ててしまった――ただただ疲れ消耗している――そのあたりまえさの中で、その五人の弟子たちが彼の許を離れたその満月の夜、彼はこの世からも完全に自由になり、あの世の探求からもまったく自由になって、その菩提樹の下で眠った。初めて彼は完全にくつろいでいた。何を発見しようという欲望もなく、何かになろうという欲望もなかった。するとその何ひとつ望まない瞬間に、彼は突然目覚め、覚者になった。ブッダフッドは、くつろいだ状態の中で彼の所に来た。
あなたたちは一二年間働きかける必要はない。あなたたちはそのくつろいだ状態から始めればいいのだ。それは仏陀の旅においては最終地点だった。それはあなたの旅の中では最初の地点にもなりうる。
そしてゴータマ・ブッダが覚醒を得たのち、最初にしたことは、自分に起こったことを分かち合うためにあの五人の弟子を探すことだった。そして彼がその五人の弟子の所に着いたとき‥‥彼らはやって来る彼を見た――それは非常に素晴らしい話だ。
彼らはこう決めた。「ゴータマがやって来る。しかし我われはもう彼には敬意を払うまい。彼はもう聖者ではなくなった。緩んだ楽な生き方をあの人は始めた」
だが仏陀が近づいてくるにつれて、その五人の弟子は全員立ち上がった。彼にどんな敬意も払うまいと決めていたのだが、その自分たちの決定にもかかわらず、彼らにはゴータマがまったく別人になってしまったことがわかった――「あの人はもう我われが知っていたあの同じ人ではない。やってくるあの静けさ、あの自足の様子。あの方は見つけたらしい」。そして彼らは全員ゴータマ・ブッダの足に触れた。
ゴータマ・ブッダの彼らに対する最初の言葉は、「私のことなど気にすまいと決めていたのに、どうしてそんなふうに敬意を払うんだね?」というものだった。
五人はみんな許しを求めた。彼らは、「あなたがあのもとのままのゴータマだと思っていたのです。私たちは――五年間も一緒にいたのですから、あなたのことは知っていました。でももうあなたはあの同じ人ではない」と言った。
光明を得るとは、大変な変容だ。その人はまったく別の人間になる。古い人は死んで、いなくなり、まったく新しい意識が、新鮮な至福が、未だかつてなかったようなある開花が、ある泉が湧き起こる。
ゴータマ・ブッダにはそれは一二年かかった。あなたたちは一二分もかける必要はない。それは自分自身にくつろぐというひとつのアートにすぎない。伝統的な禅の中では、仏陀がまだ無知だったときにやっていたことを全部やっている。そして彼らは最後にそれを捨てる。
私が言っているのは、今すぐそれを捨ててみてはどうかということだ。
あなたは今この瞬間にもくつろぐことができる。
すると、そのくつろぎの中にあなたはその光を、その覚醒を、その目覚めを見出すことだろう。
ゲスタ・イタールに起こったことが、必ずしも禅への入り口である必要はない。彼女は古い伝統的な禅の導師の仲間だったのだ。私は禅をごく単純な、無垢な、喜びに満ちた方法と理解している。そこには何も苦行などないし、生を否定するようなものは何もない――出家する必要などない、僧侶になる必要などない、僧院に入ることなど要らないのだ。あなたは自分のなかに入らなければならないだけだ。そんなことはどこでもできる。
私たちは可能なかぎり、それをもっとも単純な方法でやっている。そして禅が私がそうしようとしているほどに簡単なものになって初めて、現代人はそれに興味を持つことができる。さもないと、やらなければならないことが多すぎる――為すべきことが多すぎ、探求すべき道が多すぎ、気を散らすあまりにも多くのことがある。
禅はごくささやかな遊び心に満ちたものにならなければならない。眠りに入る時――その直前に――たったの五分であなたは自分の中に入ることができる。それで一晩中あなたの存在の中心そのものにとどまることができるのだ。それで夜中ずっと、あなたは平和で静かな気づきになることができる。身体のなかには眠りがあるだろうが、その眠りの下には夜から朝まで光の底流があることになる。
そしていったん、眠っている時にも自分のなかにある意識が存在しうるのだとわかったら、そうなれば一日中、あらゆるたぐいのことをしながら、油断なく注意して意識していることができるようになる。ブッダであるとは、ごく普通の、あたりまえの、素朴で人間的なことだ。
二番目の質問
何時もどれほどあなたの表現の美しさに打たれているか、私はことばで言い表すことができません――あなたのことば、あなたの身振り、そして今は特に、あなたの絵の中のそれに打たれます。
何も描いてない紙の前に座っているとき、あなたには正確には何が起きるのですか?人は光明を得てからも、芸術的な創造に対する衝動を持つものなのでしょうか?
禅と芸術と創造性について私たちに話していただけますか?
禅はあなたたちのどんなものも妨げない。それはその人のなかに潜在しているあらゆるものを開く。その人が画家になる潜在能力を持っているなら、禅はそれを開く――その人がそれに気づいていないとしても。詩人になるべき潜在能力があれば、禅はその能力を開く。すると初めて、その人は散文ではなく詩で考え始めている。
音楽や、踊り、あるいは科学的な探求についても同じことが言える。どんなたぐいのオリジナルな経験でも、禅はあなたに許す。それはどんなものも妨げない。禅は肯定的な、生におけるもっとも肯定的な経験だ。それは自分のなかに隠れているものすべてに、それまで覗いてみたこともなかったようなあらゆるものに気づかせてくれる。
それはただ気づかせてくれるだけでなく、その潜在能力を探求するようにもしてくれる。
禅は渇いた、砂漠のような経験ではない。それは非常に豊潤な美しい庭だ――突如として花開き始めるあなたの〈生〉のなかの泉だ。自分がそれに気づいたとき何が起きるかはけしてわかからない。それはこちら側の決定ではない、それは選択ではない。それは無選択の素朴な経験だ――あなたはある方向に向かって動き始める。と、突然その方向がじつに命にあふれ、あらゆるものをそれに捧げることができるほど魅力のあるものになる。
禅はじつに創造的な経験だ。それは他の宗教には似ていない。宗教はすべて非創造的だ。実際、いわゆる聖者は何もしない。彼らは大詩人でもなく、偉大なダンサーでもなく、大音楽家でもない。だが真の、本物の聖者、そういう人はいわゆる聖者のなかにあってごく稀にしかいないが‥‥。
つい先日、今の法王がこの四年間で二千人以上の聖職者を送り出したという情報を受け取った。免許を与えたのだ。彼は寄付できる人たち全員に許可証を与え続けている。今ではカトリック教会は世界最大の銀行を所有している――バンク・オブ・アメリカだ。カトリック教会は世界最大の土地を所有している――ほかのどの国の国有地よりも多い。
過去における方法は、戦争、つまり人殺しだった。何千何万という人びとが、その財産を取り上げるだけのために殺された。あるいはカトリック教徒になることを強いられた。カトリックの皇帝コンスタンチンひとりだけで、たった一日で一万人の人間を殺した。彼はカトリック教徒ではない者の集会をローマの大オーディトリウムで行い、「我われはローマにキリスト教徒以外の者を望まない」と言って、軍隊に全員射殺するように命じた。彼はイタリア全土にキリスト教徒になるように強制した‥‥まさに銃口によってだ。
キリスト教の全歴史は戦争以外のものではない――殺戮と暴力の歴史だ。またほかの宗教についても、劣らずに同じことが言える。それらは破壊的だ。いろいろな意味
において破壊的だ。人びとを疚しくすることによって壊し、罪人にすることによって壊し、この世と喜びをすべて放棄させ、無用な苦行に入らせることで破壊する。だが苦行に入る者は尊敬された。ところが、その苦行は病と罪の意識以外何ひとつこの世に貢献するものを持っていない。あなたたちの聖者はみな、一致団結してあなたたちに疚しさを持たせようとする。
かくて一方では彼らはこのように人類を破壊し、もう一方では自分の信徒に属さないといっては人びとを殺している。彼らは――剣によって、あるいはパンによって――人びとに強いる。過去においては、彼らは剣を持って来たものだが、今ではパンを持ってやってくる。貧しい者たちはつねに抵抗力を持たず、力によって、あるいは買収によって、改宗させられてきた。だがこんなものはまったく宗教性ではない。これは政治そのものだ。
禅は本物の宗教的経験だ。それが本物であるのは、それが人間のなかに創造性を開発するからだ。禅の導師は、誰も殺したことなどない。彼らは誰にも自分の道を強制したりしない。逆に、こちらから彼らの所に行かなければならない。しかも受け入れてもらうのは非常にむずかしいことだった。導師たちは非常に人を選ぶ。こちらからこの上ない欲望と憧れを示さないかぎり、彼らが人を招くことはない。改宗させるなどということは、問題にもならない。
あなたが井戸に行かなければならない。井戸があなたの所には来ない。井戸はあなたを招くことすらしない。それはただそこにあって待っているだけだ。
三番目の質問
エネルギーが内側に向かって行くとき、それは思考になり、気分になり、感情になります。そしてエネルギーが外に向かって行けば、それは生き物や自然との関わり合いになります。けれどもエネルギーがもう内側にも外側にも向かわなくなれば、それはただそこに息づき、振動しているだけです。その時それは存在とひとつに、全体とひとつになっています。これが坐禅なのですか?
その通りだ。エネルギーがただそこにあるだけのとき――どこにも向かわず、その源泉においてただ息づき、そこで光を放射し、蓮の花のように花開き、外側に出ても行かなければ、内側にも入って行かないとき――それはただいまここにある。
内側に入りなさいと言うとき、私が言っているのは、頭の中に入って行きつづけてはいけないということだ。
社会は全部、あなたたちのエネルギーを頭の中に注ぐように強いる。全教育はいかにしてエネルギーを頭の中だけで脈動させるかという――どうやれば大数学者になれるか、どうすれば偉い医者になれるか――という基本的技術からなっている。この世の教育はすべて、エネルギーを頭に持っていくということからなっている。
禅はあなたたちに頭から出てくるようにと、そしてその源泉に――世界中の教育制度がそこからエネルギーを引き出し、頭に注ぎこませ、それを思考に変え、イメージに変え、考えることを生み出しているその源泉に――向かうようにと求める。思考には思考の役割がある。禅が頭の中のエネルギーの役割について知らないというのではないが、そのエネルギーをすべて頭の中で使ってしまえば、人はけして自分の永遠性に気づくことはなくなる。非常に偉い思想家や哲学者にはなるだろうが、〈生〉が何であるかを自分の経験として知ることはけしてないだろう。自分の経験として全体とひとつであるということがどういうことかを知ることはけっしてなくなる。
エネルギーがただ中心で鼓動しているだけのとき‥‥。それがどちらにも向かわず、頭にも向かわずハートにも向かわず、それが、ハートがそこからそのエネルギーをも
らう、頭がそこからそのエネルギーをもらうまさにその源泉で‥‥その源泉そのもののなかで鼓動しているとき、それこそがまさに坐禅の意味だ。
坐禅とは、どちらにも向かうことなくただ源 において坐っているということだ。
ある途方もない力が湧き起こる。光と愛へのエネルギーの変容、より大いなる生への、慈悲への、創造性へのエネルギーの変容が。それはさまざまな形を取りうるが、まず人は源泉にいることを学ばなければならない。そうすればその源が、あなたの潜在能力がどこにあるかを決めることになる。あなたは源でくつろいでいればいい。そうすればそれがあなたの潜在能力そのものにあなたを連れて行ってくれる。永久に考えることを止めなければならないというのではない。ただ人は生き生きと気づきながら、しかも源に帰っていくことができなくてはならないということだ。頭が必要なときには、エネルギーを頭に移動させればいいし、愛が必要なときには、そのエネルギーをハートに移せばいい。
だが二四時間考えている必要はない。考えていないときには、自分の中心に戻ってくつろがなければならない――そのことが禅の人を絶えず満足させ、生き生きと気づかせ、喜びにあふれさせているのだ。ある至福が彼を取りまいている。それは行為ではなく、ただ放射している。
坐禅こそが禅の戦略だ。文字通りの意味はただ坐っているということだ。どこに坐っているのか? 源泉そのもののなかに坐っている。そしてたまには、中心で坐りつづけていたら、どんなマインドの活動でも何の障害もなくこなせるはずだ。あらゆるハートの活動を何の苦もなくこなすことができる。しかもなお、時間があるときにはいつでも、無用に考えることも無用に感じることもなく、ただ在ることができる。
ただ在ることが坐禅だ。
そしてもしただ在ることができれば――二四時間の中のほんの数分間だけでも――ブッダであることを自分に気づかせておくには充分だ。
経文に入る前に、伝記的な注を少し。
雲巌の弟子の洞山良介は、八○七年中国に生まれ、八六九年に死んだ。彼はもともとは唯識派に属していたが、後に禅に関心を持ち、師を求める旅に出た。
唯識派とは、聖典や祖師たちのことば、また哲学的な学問の道に関心を持っている人たちの仏教徒の呼び名だ。彼らは知的には活発だが、経験そのものに自分で入っていくつもりはない。彼らはできるだけたくさんの知識を集め、非常に賢くなる。彼らは経典に書いてある解答はすべて知っているが、自分では何ひとつ経験していない。
洞山は最初学者で、あらゆる文献を学んでいた――仏教には世界最大の文献がある。ほかのどの宗教に比べてもより多くの経典を持っている。
ゴータマ・ブッダが死ぬとすぐに、彼の弟子たちは三二の支流に分かれた。たちまち三二の学派が生まれ、別々の聖句と経典を持ち、自分こそ本物であり、唯一の真の教えであると装っていた。問題は、ゴータマ・ブッダは四二年間朝に夕に教えつづけているため、ある者はあることを聞き、また別の者は別のことばを耳にしていることだった。
四二年の間、彼は絶えずある場所から別の場所へと移動していた。当然別々の人びとがそれぞれちがったことを彼から聞いており、その人たちが経典を編集した。たちまちにして三二の分派が発生した。ゴータマ・ブッダはひとことも書き残していなかったが、それぞれの分派は自分こそが本物であると装った――「仏陀はこう語られた‥‥」と。
いまとなってはなにが実際に仏陀によって語られたことばで、なにが弟子たちによって付け加えられたものなのかを見分けることはきわめてむずかしい。そこで仏教徒の世界には大いなる学問が生まれ、そこで人びとはなにが本物でなにがそうでないかを見分けようと経典を研究している。
つい最近も、同じような学問がヨーロッパで始まった。大学教授と非常に学問的なキリスト教徒たちが特別の委員会、聖書学会を発足させた。現在この人たちはなにがイエスによって実際語られたことばであり、なにがほかの者によって付け加えられたのか――なにが虚構で、なにが神話で、なにが真実なのか――を調査している。
つい二、三日前、ポーランド人法王が全世界のカトリック教徒に、「聖書学者の言うことを聞いてはならない」と宣言した。なにしろ、聖書学者たちはバイブルに付け加えられたほんとうではないことをたくさん取り除いているからだ。出来事、奇跡、処女生誕、復活‥‥聖書学会はこういうものを全部取り除いている。彼らが聖書に関するかぎり、ヨーロッパでもっとも学術的なグループであることも認められている。彼らは二、三か月毎に会議を開き、記録を検討している。そして彼らの言うことを
聞いていたら、バイブルのほとんど九○パーセントは消えてしまう。だが、彼らは絶対的に正しい。何故なら彼らは、そのことば、その言明、こそ福音が初めてやってきたそのルーツを捜し当てているからだ。異教徒の古い経典のなかに見つかるはずなのに、イエスがそんなことを言ったものかどうか誰にも証明できないように、その経典が滅ぼされてしまったものも二、三ある。
処女生誕という考えでさえ、イエスよりも古い。それは異教徒の神、処女から生まれたと考えられたあるローマの神だった。そしてその同じ神は 磔 にされた。そしてその同じ神に復活という考えが結び付けられている。それがみんなバイブルのなかに取り込まれ編集された。その異教徒たちは滅ぼされ、その寺院は焼かれ、彼らの経典は葬られた。現在その聖書学者たちは、イエスが生きていた同時代の文献からそれらの事実を発見するための方法を見つけようとしている。
福音書のひとつはインドで書かれた。トマスの第五福音書だ。これがバイブルに含まれていないのは、それが聖書を編集し、なにを聖書に含めなにを聖書に含めるべきではないかを決めていたコンスタンチンの手に入らなかった、という単純な理由のためだ。こういうアイデアや神話や虚構がイエスの生涯に付け加えられたのは、すべてこの男のためだった。
同じことが仏典についても言える。多くのことがヒンドゥ経典から借りてこられ、多くのものがジャイナ文献から借用されている。それらは同時代の宗教だからだ。また仏陀の同時代者たちのなかにはのちに文献を残さなかった者もあるが、その人たちも仏陀が教えていたその場所で教えていた。そのため彼らの教えの多くのものも編集され、ゴータマ・ブッダの教えに混合された。
禅には仏陀本来の教えを見つけ出そうとするきわめて学問的な伝統が存在する。だがたとえなにが本来のことばでありなにがそうでないかを発見したとしても、それで光明が得られるわけではない。仏陀が語ったことばを正確に知ることにはなるかもしれないが、それで当人の意識になにか変化が起きるわけではない。
洞山は初め学者だった。そして本来の教えを知ろうとどんなに努力しつづけ、またそれを見つけたところで、自分はやっぱり無知のままなのだということに気がついた。
大学者にはなるかも知れないが、内面深くでは自分について何ひとつ知らない。そして問題は仏陀が何を言ったかを知ることではなく、自分自身の内なる仏陀、自分の内なる意識を知ることなのだ、と。
唯識派に所属していた後で、彼は禅に関心を持った。彼は学問の世界を捨て、師を求めて旅立った。彼は教師の許に、大学者の許にはいたが、彼らの誰ひとりとして導師ではなかった。
そして導師は学者である必要はない――それは必須のことではない。彼は学者かもしれないが、それはたまたまそうであるだけだ。必須の、そして肝心要なことは彼本人が知っていること、その人自身の経験だ。そこで彼はその人本人が真理のなんたるかを知り、彼に道を示すことのできる人を求めて旅に出た。
-
経文だ、
愛するOSHO、
洞山は、無生物が法を説いているかどうかについて疑問を持っていた。洞山が為山を訪れると、為山は彼に雲巌の所に行くように勧めた。
彼の探求はこの世の無生物が法 を、究極の真理を説いているかどうかということだった――この客観世界に究極の真理が見つかるかどうかということだ。
それが科学がやろうとしていることだ――対象世界のなかに究極の真理を見いだそうとすることだ。それを対象物のなかに見つけることはできない。だがそれは禅の伝統の一部であり、それもまた‥‥。
為山は自身導師だったが、彼は、洞山が学者であるのを見て、雲巌に会いに行くように洞山に勧めた。為山は学者ではなかった――彼は導師であり、自分がブッダであることを知っていた。だがこの洞山という男が哲学的疑問を問わずにはいないことを見て取って、彼を、導師でもあり学者でもある雲巌の所に送った。
雲巌の許で、洞山は初めて真理を知り、自分の経験を記録するために次のような偈を作った。
「素晴らしきかな! 素晴らしきかな!
無生物も法を説く――なんという言語に絶した真理か!」
雲巌は彼に沈黙することを教えた。そして沈黙すれば、まわりのあらゆるものが真理を述べ始めるものだ。樹も山も‥‥全対象世界が突然、真理の火によって燃え上がる。自分の実存の源において静かに坐れば、この世のあらゆるものが究極なるものを指し示す。
自分の源を発見したとき、彼はこの偈を書いた。
「素晴らしきかな! 素晴らしきかな!
無生物も法を説く――なんという言語に絶した真理か!耳で聞こうとすれば、けっして理解することはできない。
眼に聞こえて、初めて本当にわかる」
彼は第三の眼のことを言っている。内側に入ってゆくにつれて‥‥、人のエネルギーは頭のなかにある。まずそれは第三の目を通り抜けなければならない。深く入ってゆくにつれそれは第四のセンターであるハートを通り抜け、全エネルギーが第一のセンターに来る。そこからそれは頭にある第七のセンターに向かって再び上昇しうる。
しかし、第七のセンターにいつまでも引っかかっていたら、けっして真理のなんたるかを経験として知ることはない。人は自らの実存の谷底の深みにまで下りなければならない。自分が全体とつながっているその根源そのものにまで到達しなければならないのだ。
雲巌は彼に、「嬉しいか?」と訊いた。
洞山は答えた。「嬉しくないとは言いません。しかしその嬉しさたるや、ゴミの山に輝く真珠を見つけたようなものです」
光明を得てしばらくして後、洞山は中国全土を旅し続けた。
彼が言っているのは、自分で見る以外にそれを知る方法はない、ということだ。他の誰からも、聞くことはできない。どんな覚者にも説いてはもらえない。どんな導師からも教えてはもらえない。そういう人たちみんなができるのは身振りで教えることでしかない。そういう人たちはみんな月を指さすことしかできない。だがその指は月ではない。あなたはその指を見るのを止めて、月そのものを見始めなければならない。自分で月を見れば、その美しさはわかる。月をさす指を見ることで、その美しさを知ることはできない。
知識はすべて月を指し示すものだ。あらゆる経文、あらゆる経典は月を指し示している――月をさす指にすぎない。ところが人びとはその指にこだわり、問題は指ではないことを完全に忘れてしまう。月は遥か彼方にあり、指はその方向を示しているにすぎない。その指にこだわってはいけない。指のことは忘れなさい。あらゆる知識、あらゆる経典を忘れ、自分で自分の真理を見るのだ。
それは耳の問題ではない。それはまさにあなたの眼、あなたの内なる眼の問題だ。自分の内を見ないかぎり‥‥それを聞いたり、それを読んだりすることによって知ることはできない。多くの知識をえることが覚者になることではない。そうではなく、無垢の子どもになること、どんな深刻さもなく、嬉しげに、上機嫌に踊りながら、遊び心を持って源にたどり着くことが‥‥。自分のエネルギーを源そのものに集めて、そこにしばらくの間いてごらん。そうすれば、あなたは新しい経験によって満たされ、その経験は日毎に成長しつづける。
やがてあなたは自分が光で満たされていることに気がつく――満たされているだけでなく、光が自分の身体から放射し始める。それがオーラと呼ばれて来たものであり、ウィルヘルム・ライヒが科学的に証明しようと試みていたものだ。だが人びとに彼の語っていることが理解できなかったために、彼は気違い病院に強制収容された――
「何の放射のことを奴は言ってるんだ?」と。
だが現在ではキルリアン写真が、肉体のまわりにある生命のオーラを写真に撮ることができる。健康であればあるほど、その人のオーラは大きい。幸せであるときには、それは本人のまわりを踊り、不幸であればそれは縮む。キルリアンが不幸な人を被写体に使ったときには、その写真にどんなオーラも見つけられなかった。オーラが内側に縮まってしまったのだ。だが彼が、踊り、楽しみ、嬉しげに野の花を摘み、浜辺の石を集める子どもたちを撮ったときには、そのまわりに途方もないオーラが出ていた。
その同じオーラが覚者たちのまわりにあった。そして、仏陀やクリシュナの時代には写真など手に入らなかったにもかかわらず、絵画や彫刻が全部オーラを持っているのはほとんど奇跡と言える――頭のまわりのあの光輪だ。
ひとたび自分の生命の源を見たら、人は同じ光がこの世のあらゆる対象、この世のあらゆる人から放射しているのを見始める。オーラを見れば、その人が不幸なのか、あるいは幸せなのかを見て取ることができる。
導師の雲巌は彼に、「嬉しいか?」と訊いた。
洞山は学者だったから、覚者の話し方は知っていた。そして今や彼は自分でそれを経験した――そのことを彼の解答に見ることができる。彼は言う。「嬉しくないとは言いません。しかし嬉しいとは、あまりにも月並みなことばです。嬉しいと言ってみても、何も言ったことにはなりません。私が見つけたものはあまりにも大きく、それは『嬉しい』というようなことばでは言い表せません。もっとずっと大きいものです。だから、嬉しくないとは言いません。わかっていただきたい、それは嬉しいというようなことより大きなものです。ことばでは説明できません。言えるのは、私はゴミの山のなかに輝く真珠を見つけた、ということだけです」と。
彼が言っている「ゴミの山」とは、彼の学問のことだ。彼は要もないのにたいへんな知識を蓄積した。ところがその知識は、本来の存在――存在に対する自分の根拠そのもの――の上にただ積み上げられ、それを隠していただけだった。
それはあたりまえの幸福ではない。実際それを説明できるようなことばはない。「至福」ということばはやや近い。「恩寵」ということばはもっと近い、「歓喜」ということばはもっと近い。だがそれ以上はどんなことばも存在しない。その経験は、歓喜そのものよりも遥かに深い。
光明を得てしばらくして後、洞山は中国全土を旅し続けた。ある日、彼は?潭に着き、初首座に会った。初は、洞山に挨拶して言った。
「素晴らしや、素晴らしや――道と仏道の世界は測り知れぬ!」
初は洞山に挨拶し、その挨拶の言葉の中で「素晴らしや、素晴らしや――道と仏道の世界は測り知れぬ! 私はあなたの中にブッダとタオの出会いそのものを見ることができます」と言った。
これこそそのたぐいのことだ。洞山は「わしはそういう世界のことは知らぬ。そういうことを語っているそなたは誰か?」と応えた。
彼は初に、それはことばを超えたものだと指し示している――自分の内側を見なさい。誰がそのことばを言っているのか? 何処からそのことばが来るのか? その源はことばを超えている」と。
初首座が黙したままなので、洞山は、「言え!」と声を上げた。それで初は「急かせてはいけません。それこそ道を逃すやり方」と言った。
洞山は「口にもされておらぬものを、急かせるも、見逃すもあろうか?」と応えた。 初はそれに応えられなかった。
そこで洞山は、「仏と道――次に君は経について語るだろう」と言った。
「最初君はブッダとタオについて言及する。次には経文について話し始めるだろう。ひとたび話し始めたら、話すことに終わりはない。そして君が話そうとしているものはことばを超えている」
初は「これについて経にはなんとあるか?」と応えた。洞山は「なにもかもわかったら、ことばは忘れる」と言った。
初は「それは心の病」と言った。洞山は「この病は軽いか重いか?」と言った。初は洞山に応えることができなかった。
それこそ為山が彼を雲巌の許に送った理由だった。洞山は大変な学問の人で、ひとたび自分でブッダを発見すれば、非常に偉い導師になるべき者だった。普通の教師には彼のことばを理解することもできない。初は道教と仏教、両方の普通の教師だった。そして見てもわかるように、洞山は仏 も道も否定した。そういうことばは指し示す
ものでしかなく、説明するものではない。そこで彼は初に、「話しつづければ、やがて君は経文について話すことになる」と言った。
あなたたちには彼の哲学的アプローチがわかるはずだ。彼が真理を発見したいまとなっては、ただの学者である者には、彼と話しをすることすら非常にむずかしい。彼にはどんな学者もごく簡単に打ち負かせる。
洞山がブッダもタオも経験そのものではない、と言っていることに気がつき、初は教師として「それについて経文はなんと言っているか?」と言った。彼はまだ経文のことを話している――「この不可知なるもの、説明し難きものについて経文はどう言っているか? あなたはそれが仏 をも道も超えていると言っておられるが」と。
洞山は言った。「なにもかもわかったら、ことばは忘れる。いったん自分でそれを知ったら、一度自分でそれを味わったら、人は沈黙する」と。もちろん教師はこの点で同意しない。
初は腹を立てて、「それは心の病」と言った。洞山は、「その病は軽いか重いか?」と言った。
何の病か? それは病ではないのだが、教師はマインドに捕らわれている。あなたはそれはマインドを超えたものだと言っているが、無意味なことを言っているにすぎない。あなたは病気だ。あなたは気違いだ、あなたは正気ではない、と。教師はマインドに捕らわれている。導師はマインドを超えてる。
初は、その病は軽いか重いかという洞山の問いに応えられなかった。
ある日、僧の秋の坊が友人の詩人を訪ねた。お喋りをしていて、詩集を作ったことに触れた――一日一句を作るのだと言う。彼は一句を詠んだ。
正月四日
よろづ此世を
去るによし
その日はまさに一七一八年一月四日だった。その一句を読み終わるや否や、秋の坊は頷 き、そして死んだ。
禅の導師は、生き方を知っている、そして死に方も知っている。彼らは生を深刻なものとは思わないし、死も深刻には受け取らない。深刻さは病んだ存在の見方だ。完全の人は生を愛し、また死を愛する。彼の生はダンスになり、そして彼の死は歌になる。生と死の間に何の区別もない。
マニーシャの質問だ。
愛するOSHO、
哲学者のカール・ヤスパースは、彼の著書『哲学』の第三巻に「実在についての真の問いを問うためには、人は次のような識別をすることによって思考し、研究し、自らを方向づけなければならない‥‥。即ち、実在とは計測可能なもの、私たちの感覚が法則に則った時空のなかで捕らえることができるもの、少なくとも適切な尺度をもってすれば、操作し、あるいは計算することが可能なものだ」と。
コメントしていただけますか?
マニーシャ、カール・ヤスパースは大哲学者だが、導師ではない。彼が言っていることこそ物質の定義だ。「物質」ということばはまさにサンスクリットのマトラという単語から来ている。マトラとは測ることができるものという意味だ。物質とは計測可能なもののことだ。そして測ることのできないのが、あなたたちの実在だ。
カール・ヤスパースは実在と物質とを混同している。物質はリアルなものだが、実在はそれより遥かに大きなものだ。それは計測不可能な意識をも含んでいる。あなたは何フィートの、何マイルの、あるいは何キロの意識を持っているか‥‥?
物質は測ることがきるものであり、意識は測ることができないものだ。そしてヤスパースは、物質を唯一の実在としてそこに自分を閉じ込めている。彼は完全に間違っている。物質に関しては彼は正しい。だが実在については彼は間違っている。実在とは、物質よりずっと大きなものだからだ。
カール・ヤスパースにも自分が何キロの意識を持っているかを言うことはできない。
意識を測る手段はない。そして疑いもなく、カール・ヤスパースでさえ彼が意識を持っていることは否定しえない。『誰が』それを否定しているというのか?
ムラ・ナスルディンのある小さな話しを思い出した‥‥。
彼はレストランで何人かの友だちに、自分の気前のよさについて話しているところだった。友人たちは、「君は気前がいいと口で言うだけで、俺たちは君が気前のいいところなんか一度も見たことがないぜ。俺たちを呼んで、お茶の一杯もご馳走してくれたことがないじゃないか」と言った。
「いいとも! 君たちをみんな招待するよ。このレストランの全員だ。家で夕食をご馳走しよう」とムラは言った。
みんなには信じられなかった。みんなは彼が非常にけちだということを知っていた。
彼はただ自分の気前のよさを自慢しているところを捕まっただけなのだ。みんなが彼の家に近づくと、ナスルディンは妻のことに思い当たり、自分が無用な面倒を持ち込んだことに気がついた。今となってどう女房を説得しようか? 第一彼は朝、野菜を取りに家を出たのだった。それが今では、人をたくさん連れて戻って来ている。
そこで彼はみんなに向かって言った。「あんたたちも亭主と女房の間の問題はわかるはずだ。ちょっと二、三分外で待っていてくれ。私が最初に入って、ちょっと友だちを招待したことを女房に納得させるから」
そこで彼はなかに入り、扉を閉め、誤って自分がたくさんの人間を招待してしまったことを女房に告げた――「こうなったらお前が何とかしてくれ」
「私になにができるっていうの? 家にはなんにもないわよ。あなたは一日中外に出てるし‥‥野菜もないわ」と妻は言った。
ムラ・ナスルディンは言った。「そんなことは問題じゃない。ただ戸口に行ってみんなに、どうしてそんなところに集まってるのかって訊けばいいよ。もちろんみんなは、俺に夕食に招待されたんだと言うだろう。お前は、そんなことはただ否定するんだ。ただ『ムラ・ナスルディンは朝から出かけたまま家にはいません』と言えばいい。行ってみんなに『帰って下さい。あの人は家にはいません』って言うだけでいいんだ」
妻は戸惑ったが、何とかしなければならなかった。そこで彼女は扉を開けた。そしてムラ・ナスルディンは、二階からどうなることかと見守っていた。女房は「うちの人は家にいませんよ。皆さん誰を待っているんですか?」と言った。
みんなは「彼は僕らと一緒に来て、目の前で入って行ったんだ。僕らがみんな証人だ。彼は僕たちを夕食に招待したんです――おそらくあなたは知らないんだろうけど、彼は家のなかに入ったんですよ」と言った。
「あの人は家のなかにはいません」と女房は言った。
みんなは言った。「そいつは変だな。僕らは彼と一緒に来たんだ。彼がここで待っているように言ったんですよ。なかに入って見つけて下さい。きっとなかで見ているか、それともあなたのことを探してますよ」
妻はどうしてもみんなをなかに入れようとしなかった。みんなはなかに入ろうとした。みんなは「僕たちはみんなあなたのご主人の友だちだ。僕らになかを探させて下さい!」
ムラは状況を見て、二階から大声を上げた。「そんなのはまったくむちゃくちゃだ!
女房がなかにいないって言ってるんだから、彼はなかにいないんだよ! かわいそうな女をいじめてお前ら恥ずかしくないのか? 彼は君たちと一緒に来たかもしれないが、裏口から出て行ってしまったかもしれないじゃないか?」
それを本人が自分で言っているのだ‥‥。
ちょっとカール・ヤスパースに、「あなたの意識は惨めですか?」と訊いてみるといい。もし彼が、意識を持っていることを否定すると言うなら、誰がそれを否定しているというのか? 彼はそれを否定するか受け入れるかしなければならないはずだが、いずれの場合にも――その彼の否定でさえ――意識の存在を証明することになる。
これはカール・ヤスパースだけでなく、世界中の哲学者すべてについての不思議なことだ。彼らは物質だけが存在すると言いつづけている。物質は目によって、耳によって、手によって、あらゆる人間の感覚によって経験されうるからだ、と。それは測ることができるものだから、それゆえそれだけが唯一の実在だ、と。だが真実は、計測しえないものの存在を否定する者でさえ、その否定のなかでさえ意識を受け入れているということだ。そうでないなら、誰がそれを否定しているのか? カール・ヤスパー
スのような非常に知的な人間、今世紀の非常に偉い哲学者が愚か者のように語るのはじつに驚くべきことだ。だが哲学者はすべて愚か者のように語る。彼の、計測可能な物だけが実在だということばは完全に間違っている。計測可能なものは物質だ。そして、計測不可能なものも実在しており、それは意識だ。
私たちの探求は計測しえないものを求めてのものだ。計測可能なものは科学者に残しておいてやればいい。神秘家が問題にするのは計測不可能なものだ。
さて、サルダール・グルダヤル・シンの時間だ‥‥。
元海賊のコドフィッシュ船長が、ある晩石鴎亭で自分の海での生涯の話しをしているところだった。
「ある時オウムを一羽飼っていてな」とラムを飲みながらコドフィッシュが言った。
「信じられんような奴だったよ! 何だって真似できるんだ――チャーリー・チャップリンでも、ジャック・ザ・リッパーでも、マリリン・モンローでも、ポープ・ザ・ポラックでも‥‥ナンシー・レーガンだってな!」
「へえ!」とバーテンのイゴールが言う。「今はどこにいるんです? その鳥はどうしたんですか?」
「ああ!」と老海賊は嘆きの声を上げる。「苦しいときがあってな、食うものがなくて――俺が食っちまったんだよ!」
「自分のオウムを食べたんですか?」と嫌悪の面もちでイゴールが声を上げる。
「いったいどんな味でした?」
「まさに七面鳥の味よ」とコドフィッシュは答える。「あのオウムときたら、何だって真似できたからな」
パディはある夜遅くまでパブにいて、店が閉まるとぐでんぐでんに酔っぱらって外によろけ出る。家への道を思い出そうとしながら、通りを歩き回っていたが、とうとう諦めた。パディが道に座り込んでまわりを見回していると、やっとタクシーが彼の隣までやって来た。
「ああ!」とパディはうめき声を上げて車の後ろに這い上がり、座席の上に横になる。「ファーガス通りの五番地までやってくれや」
タクシーの運転手はパディの様子をじろじろと見てから答えた。「旦那、ここがファーガス通りの五番地ですよ!」
「ああ!」とパディはうめき声を上げる。「わかった! だけど、この次はあんまり飛ばすなよな」
オーストリーはウィーンのある霧の朝、ふたりの有名な精神分析学者ジークフリード・マインド博士とクレージー・カール・コング博士が小さなブラウン・ダニューブ・カフェで出会う。
コーヒーとクリームケーキを並べたテーブル越しに、コング博士が突然飛び上がってジークフリード博士の首根っこを捕まえて揺する。
「今度こそ行かなくちゃならんぞ!」とカールは叫ぶ。「これまで六回も思い立ったんだ! 我われはミイラを見にエジプトのピラミッドに行かなくちゃならん!」
「ミイラだって?」ジークフリードは悲鳴を上げ、失神してクリームケーキの中に倒れ込む。
コング博士はマインド博士が息を吹き返すまで、その頭にコーヒーを注ぐ。
「しっかりしろ、マインド!」、相手の頬をぴしゃぴしゃ叩きながらコング博士が叫ぶ。「できるとも! 我われはこの死の神秘を探検しなくちゃならん!」
「死だって?」マインドは悲鳴を上げ、再びクリームケーキの皿の上に気を失う。
三○分後、ウィーン空港でクレージー・カール・コング博士が、ジークフリード・マインド博士のカラーを引きずってカイロ行きの飛行機に乗り込む。
「しっかりしろ、マインド!」クレージー・コングは息を切らして叫ぶ。「ここまで来たんだ、あのミイラを見に行かなくちゃ!」
「ミイラ?」ジークフリードは悲鳴を上げ、スチュワーデスのネリー・ニッカーの頭の上に倒れ込む。
コングとネリーはマインドを彼の席まで引きずってゆき、安全ベルトにくくりつける。飛行機は飛び立ち、三時間後ピラミッドの国に到着する。コングはワアワア言っているマインド博士を連れ、ファラオの墓まで運ぶべく彼らを待っている駱駝のところまで連れてゆく。
コング博士はガイドのアブドゥール・バブールに、「ミイラの所にやってくれ!」と叫ぶ。
「ミイラ?」マインドは悲鳴を上げ、気を失って駱駝の背中からまっ逆さまに落っこち、砂漠の砂に鼻をつっこむ。二日後、有名な精神分析学者と彼らの駱駝は巨大なピラミッドに到着する。コング博士は飛び降り、松明をつけて、マインド博士のカラーを掴むと彼を神秘の地下室の暗闇のなかへと引きずり始める。
突然闇のなかで、コング博士が何かにつまずく。
「どうしたんだ?」とマインドが悲鳴を上げる。
「ああ、大丈夫――ただの猫の死体だ」とコング博士。
「死体!」マインドは悲鳴を上げ、気絶して倒れる。
「しっかりしろ、ドクター」とコングは叫ぶ。「もう、すぐそこまで来てるんだ」
そしてコングはジークフリードの靴を掴み、巨大な金の棺の方に彼の足を引きずってゆく。「立て!」と、マインドを壁にもたせかけ、燃える松明を彼に手渡しながら、コング博士が叫ぶ。
そして、クレージー・カール・コングは身を乗り出し、きしみを立てる重い棺の蓋を持ち上げる。蓋が大きな音を立てて地面の上に落ちる。埃が静まると、コング博士が目を見開き、口をあんぐり開けて目前の不気味な光景を見つめている。
彼は振り向くと死んだように硬直しているマインドのカラーを掴み、彼の顔を棺の上に押し付ける。
「ほら!」とコングは勝ち誇って叫ぶ。「これがミイラだ!」
「マミー?」ジークフリードは悲鳴を上げる。だが彼は目を飛び出させたまま、信じられないように見つめているだけだ。
「マミーだって?」彼はまた悲鳴を上げる。「おい、こいつはパパの方が似てるよ!
」
時間だ、ニヴェダノ‥‥。
(ドラムの音)
(ジベリッシュ)
ニヴェダノ‥‥。
(ドラムの音)
静かになりなさい‥‥。目を閉じて‥‥自分が凍りついたように感じなさい。
今こそ内側に入って行くべき瞬間だ。
自分の全エネルギーを、全身全霊の意識を集めて、深い憧れと切迫した力を込めて、内なる中心に向かって突き進みなさい。
その中心は肉体の内側、臍の下わずか二インチのところにある。
より速く‥‥そしてより速く‥‥。より深く‥‥より深く‥‥。
存在の中心に近づくに連れて、大いなる沈黙があなたの上に降りてくる。そして平安のなかに、至福のなかにあなたの全内面を満たす光がある。それがあなたの本来の姿だ。それがあなたのブッダだ。
この瞬間自分が肉体ではないということ、マインドではないということ、ハートではないということ、純粋に見守っている自己、純粋な意識であることを目撃しなさい。
これがあなたのブッダフッドだ。あなたの隠れたる本性、あなたの宇宙との出会いだ。
これがあなたの根源だ。
くつろぎなさい‥‥。
ニヴェダノ‥‥。
(ドラムの音)
くつろぎなさい‥‥そしてただ静かに見ていなさい。
あなたは海の氷のように融け始める。ゴータマ・ザ・ブッダ・オーディトリウムは意識の大海になる。あなたはもはや切り離されてはいない――これがあなたの存在との一体性だ。
存在とひとつであることがブッダであることだ。それがあなたの本性そのものだ。求めることでもなければ、見つけることでもない。いまこの瞬間にあなたはそれだ。あらゆる花々を、その香りを、その炎と火を、その測り難きものを集めなさい。そして戻って来るときそれを一緒に持って来なさい。
ニヴェダノ‥‥。
(ドラムの音)
安らぎに満ち、静かに、ブッダとして戻って来なさい。
しばらくの間、目を閉じたまま、自分が見つけたその道とその源を、自分が経験したそのブッダである本性を思い出していなさい。この瞬間、あなたたちはこの地上でもっとも祝福された人たちだ。自分自身をブッダであると思い出すことこそが、もっとも貴重なる経験だ。なぜなら、それがあなたの永遠性、それがあなたの不滅性だからだ。
それはあなたではなく、あなたの存在そのものだ。あなたは星々と、樹々と、大空と、海とひとつだ。あなたはもう切り離されてはいない。
仏陀の最後の言葉は正念だった。
自分がブッダであることを覚えていなさい――正しい思い(サマサティSAMMASATI)。
~OSHO~
-
(OSHO Times International日本版32号掲載) 2004 OSHO International Foundation