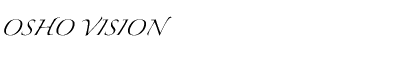OSHO 講話

The Extraordinarily Ordinary Cat ~並外れて普通の猫
“The Open Secret # 18”より抜粋 –
昔、勝軒という剣術家がいたが、彼は家に住み着いた獰猛なネズミに困り果てていた。このネズミは昼日中でも巣穴から出てきて、ありとあらゆる悪さをするほどの大胆さだった。
勝軒は自分が飼っている猫にこのネズミを捕らせようとしたが、とても太刀打ちできるものではなく、逆に噛みつかれ、悲鳴を上げて逃げ出す始末だった。そこで剣術家は近所の家で飼われているネズミを捕る技と勇気に特に優れているという猫を何匹か借りてきた。
この猫たちもネズミを捕まえることはできなかった。ネズミは隅に追い詰められると、猫たちが近づくのを見ていて、一匹一匹に猛烈な反撃をした。猫たちは恐れをなしてほうほうの態で逃げ出した。
師匠はがっかりして自分でネズミを退治しようとした。木刀をとってネズミに近づいたが、さすがの熟達した剣士の技でも歯が立たず、ネズミはまるで鳥か稲妻のように宙を飛んで、木刀をめがけて飛びかかってきた。
勝軒がその動きに応じるよりも先に、ネズミはやすやすと彼の頭の上を飛び越してしまった。彼は大汗をかいて追いかけたが、とうとう最後には諦めるよりほかになかった。彼は最後の頼みの綱に、その神妙な技でネズミ捕りの名手と評判の高い猫を近所から借りてくることにした。
この猫には、それまでネズミと戦わせるために連れてきたほかの猫と比べて、なにひとつ特別なところはなかった。まったくありふれた、どこにでもいるような猫だった。
剣術家はあまり期待していなかったが、この猫をネズミがいる部屋に連れていった。猫は部屋にはだれも不審な者はいないかのように静かに悠々と入っていった。
ところがネズミのほうは、相手が近づいてくるのを見ただけでひどくおびえてしまい、まるで凍りついたように、部屋の隅で動かずにじっとしていた。猫は平然とネズミに近づいてその首をくわえて出てきた。
黒猫が前に進み出て尋ねた。「私は武術の技では誉れの高い名家に生まれました。子猫のころから将来はネズミ捕りの名人になるべく鍛錬してまいりました。七尺もある屏風を飛び越すことができますし、ネズミしか通れないような穴をくぐる技も心得ています。ありとあらゆる離れ業を演じることができます。またネズミに私がぐっすりと眠り込んでいるかのように見せかけて、そばに近づいたら飛びかかるという知恵を使うこともできます。天井を走るネズミでさえ私からは逃れられません。今日、あのしたたかなネズミの前からすごすごと引き下がったことは不名誉のきわみです。
くだんの老練な猫は言った。「おまえが習ったのは小手先の技にすぎない。おまえはつねに敵とどのように戦うかということに腐心している。いにしえの師家が各種の技を編み出したのは武道を極める適切な道筋に親しませるためだった。そしてこの道筋は本来は単純で効果的なもの、武道のあらゆる極意の要諦であるはずだ。師家に従う者は彼の原理をつかみそこね、技の賢さや小手先の技術をいかに磨くかで頭がいっぱいになってしまう。それでも目的は達せられ、知略も格段に的確な進歩したものになろうが、帰するところそれがいったいなんになるのか? 理知とは心の働きにほかならないが、それは道に調和していなければならない。後者がなおざりにされて、たんなる賢さだけが目的とされたなら、それは道から外れて誤用されることになってしまう。これを武道の極意としてよく心得ておくがいい」
虎猫が前に進み出て自分の観方を次のように述べた。「私の思うところ、武道の極意は精神(気、中国語ではチ)にあります。私は長らくこれを養って鍛えてまいりました。私はいまや天地を満たすほどの勢いのある精神を備えるにいたりました。敵に対面したときには、すでに気迫で相手をしのいでいますから、実際に戦う前から私の勝利が決まっています。どのような戦法をとるかを意識してもくろんでいるわけではなくて、それは情況の変化に応じて自然に出てくるのです。
例えばネズミが天井の梁を走ったとしても、私が気迫を込めてにらみつけると、相手は自分から落ちてきて捕らえられてしまうのです。しかし、あの正体の知れないしたたかなネズミは影も残さずに動いていました。とても私の及ぶところではありませんでした」
古猫はこれに次のように答えた。「おまえは自分の精神力に最大の働きをさせるすべを心得ているが、その心得ていることそのものが妨げになっている。おまえの強い精神力は敵に対立しているが、自分のほうが相手よりも強いことに確信がもてない。相手のほうが優っている可能性もつねにあるからだ。自分では活発な浩然たる精神が天地を満たしていると感じたとしても、それは気迫そのものではなくて、その影のようなものにすぎない。
それは孟子の言う『浩然の気』に似ているようにも見えるが、実際にはそうではない。世に知られた孟子の浩然の気(精神)は輝かしく啓発的なもので、それゆえに気迫に満ちているが、おまえは情況に応じて気迫を得ているにすぎない。もともとこの違いがあるので、おのずとその用い方にも差が出てくる。一方の大河は休みなく流れているが、もう一方は大雨が降ったら洪水になるにしても、それ以上に強い激流に出会うとじきに力尽きてしまう。『窮鼠かえって猫を噛む』と言うではないか。
隅に追い詰められて、生死を賭けて戦っているときに、死に物狂いの相手は少々の傷など受けても当然だと覚悟している。この精神的な態度が襲ってくるあらゆる危険を寄せつけないのだ。その全存在が戦う気迫(精神または魂)の塊と化しているから、その鋼のような抵抗にはどんな猫でもかなわない。」
今度は灰毛の猫が静かに前に進み出て言った。「あなたがおっしゃったように、どれほど強い気迫であろうとそれには影が伴っていて、それがどれほどかすかなものであっても、敵はけっしてこの影を見逃さないのです。この考えに基づいて、私は長らく自分を鍛錬してまいりました――敵を威嚇しないように、戦いを強いないように、むしろ柔軟な和の心をもつようにと。敵が自分よりも強いとわかったら、私は自分をしなやかにして、相手の動きについていきます。
まるで石を投げつけられた暖簾がゆらゆらと揺れるようなものです。どんなに強いネズミでも戦うすべを見つけられません。しかし、私たちが今日、相手にしたあのネズミは手強いやつで、気迫に負けるということもありませんし、私のしなやかな気の遣い方にも揺るぎませんでした。
まったく正体がつかめませんでした――あんなやつに会ったのは生まれて初めてです」 古猫は応えて言った。「おまえの言うしなやかな気迫は自然と調和していない――それは人工的なもので、意識的な心が考え出したもくろみにすぎない。このような手段によって敵の積極的で熾烈な攻撃精神を制しようとすれば、相手はただちにおまえの心のなかのわずかな動揺でも察知してしまう。わずかでも動揺があったら正しい知覚力や動きの機敏さが損なわれてしまう。なぜなら、それが本来の自然で自発的な動作の流れを妨げてしまうからだ。『自然』に、その物事を成就する神秘的なやり方を発揮させようとするなら、おのれ自身の考え、もくろみ、意図を捨て去るしかない。
自然の成り行きに身を任せ、内側のそれに自由に振る舞わせるなら、相手に察知されるような影も、形跡も、手がかりも生まれてこない。そうしたらおまえに抵抗できるような敵はひとりもいなくなる。しかしながら、私はおまえがこれまでに経験してきた修練がなんの役にも立たないと言っているのではない。いずれにしても、道はそれが収まっている器によって示される。技術的な工夫にも妥当性(理)があるし、精神力も体のなかでそれなりの威力を発揮し、それが自然と調和したときには、周囲の変化に完璧に呼応して働くだろう。柔軟な精神がこのように保たれるときには、体と体がぶつかり合う次元の戦いは終わりを告げて、岩をも打ち砕くことができるようになる。
だが、ここにそれが顧みられないかぎりすべてが本末転倒になってしまう本質的な事柄がある。それは、自意識の考えをみじんも抱かないということだ。自意識が心のなかにあったら、おまえのすべての行いは我意から出たもの、人為的なトリック、道と調和しないものになってしまう。そうなれば人びとはおまえのやり方に従わないようになるし、心のなかでは敵対心を養うようになる。
もしも心が『心がない』(無心)と言われる状態にあるとしたら、おまえは人為的なもくろみにいっさい頼ることなく自然と同調して振る舞うことができるだろう。だがしかし、道はあらゆる制限を超えており、私のこのような評釈も本来が無尽蔵であるはずの道には遠く及ばないものである。
以前、隣村にいつも眠りこけてばかりいる猫がいて、獣としての生気を少しも示さず、まるで木に彫った作り物のようだった。だれもその猫がネズミを捕るところを見たことがなかったが、その猫が歩き回るとネズミたちは恐れをなして一匹も目の前に出てこなかった。私はあるときその猫のもとを訪ねて理由を尋ねた。だが、その猫は答えてはくれなかった。四度も同じ質問を繰り返したが、それでも黙っていた。その猫は答えたくなかったのではなくて、実を言うと、なんと答えたらいいかわからなかったのだ。これからわかることは、知っている者は一言も語らないし、語る者はなにも知らないということだ。
その老猫は自分のことばかりか周囲のことまでも忘れていた。計らいのなさという最も高い境地に達していた。あの猫は一匹たりとも殺さない武道の真髄を悟っていた。私などあの境涯にはとうてい及ぶべくもない。だが、一言も言ってはくれなかったにせよ、私はその公然の秘密を会得することができた。ただ目の前にいるだけで、この猫は並外れて普通の猫であるという単純な事実を知ることができた。ほかにはなにもいらなかった。
自分のありふれた現実を生きる者は、タオ(道)を生きているから、あらゆることが可能になる。それ以来、私はごく当たり前に生きてきた。学んだことなどはすべて忘れてしまった。実際、私は『個』としてはいなくなり、自然がなんの差し障りもなしに働くようになった。これこそが無為の為、無活動を通じた活動というものであり、これこそが私の秘密なのだ」
(OSHO Times International 日本版104号/発行Osho Japan) 2004
OSHO International Foundation